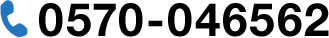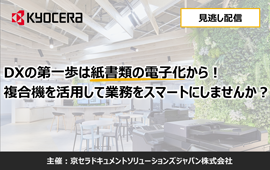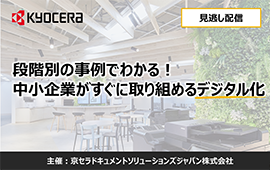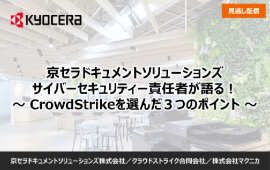業務平準化とは?標準化との違いやメリット、実施方法を解説
2025.4.9
業務効率化

ビジネスシーンでは、業務の負荷やスケジュールのばらつきが大きく、リソース配分に課題を抱えている企業が少なくありません。そこで注目されているのが、「業務平準化」の施策です。業務平準化によって現状よりも業務の効率性や安定性が高まることが期待されます。
本記事では、業務平準化に関する基礎知識を解説します。業務平準化によってもたらされるメリットや、業務平準化を実施する方法、おすすめのソリューションまでご紹介するため、ぜひ参考にお読みください。
本記事では、業務平準化に関する基礎知識を解説します。業務平準化によってもたらされるメリットや、業務平準化を実施する方法、おすすめのソリューションまでご紹介するため、ぜひ参考にお読みください。

お役立ち資料
アナログ業務の効率化、作業ミス削減を実現する方法は?
本資料では、現場におけるアナログ業務の弊害、解決方法、解決事例をご紹介します。現場業務の効率化やミス削減を推進している方におすすめです。
業務平準化とは
業務平準化とは、業務の負荷やスケジュールなどを均一化して、効率的かつ安定した作業を実現するための取り組みのことです。業務で発生する繁閑の差を抑えて、リソースを適切に配分できる状態を目指します。また、特定の従業員のみ仕事量が増加し、負荷が集中してしまうことを防ぐ目的もあります。主に製造業やサービス業といった業種で導入が進んでいるものの、他の業種でも業務平準化を応用した業務改善が可能です。

業務平準化できていない原因は?
業務平準化を実現できず、課題を感じている企業が少なくありません。その要因として、リソース配分や業務プロセスの最適化が不十分であることが考えられます。これにより、一部の従業員に業務が集中してしまい、「業務の属人化」を招くおそれがあります。特に、現状の業務の全体像が可視化されていない場合は、従業員間の業務分担がブラックボックス化しやすいため注意が必要です。このほかに、業務の性質から繁閑の差が大きくなりやすく、特定の時期に業務が偏りやすいことも要因として挙げられます。
業務平準化と業務標準化の違い
「業務平準化」とよく似た用語として「業務標準化」があります。前述した通り、「業務平準化」の目的は業務負荷の分散や作業時間の均一化などです。一方で、「業務標準化」では作業手順や作業内容を一律化することで、業務効率を向上させる目的があります。両者は目的が異なる施策ですが、組み合わせて取り組むことにより、業務改善の効果を高めることが可能です。
業務平準化を行うメリット
企業が業務平準化の施策に取り組むことで、以下のメリットが期待できます。業務平準化の推進を目指すご担当者様は、あらためて施策のメリットをご確認ください。

作業負荷の均一化につながる
業務平準化を推進すると、従業員の作業負荷の均一化につながります。社内全体のリソースを効率よく活用して、従業員ごとの仕事量のばらつきを抑えられます。仕事量の多い従業員の疲労が軽減され、過剰な残業や過度な労働の負担を防ぎ、健康的な職場環境を実現できます。 また、離職率の低下が期待できることもメリットです。
生産性を向上できる
業務平準化によって作業効率が高まると、生産性向上の効果が期待できます。業務中に生じる無駄な待ち時間や労力が削減されることで、従業員の業務への集中力が維持され、生産効率が高まります。また、リソースに余剰が生じた場合は、別の重要性の高い業務へ充てて活用することが可能です。
業務品質を安定化できる
業務平準化は、業務品質の安定化にも有効です。業務に必要な時間を十分に確保することで、ミスや品質低下が抑えられて、サービスや成果物の品質向上が期待できます。顧客へのサービス提供の一貫性が高まり、企業やブランドへの信頼性が向上するのがメリットです。
コスト削減につながる
業務平準化の一環で作業の無駄をなくすことで、不要なコストを削減できます。業務プロセスの効率化にともない、長期的な視点で経営コストを抑えられるのが大きなメリットです。例えば、繁忙期の残業による人件費増加や、リソースの過剰投入などを防止できます。
業務平準化を行うときの懸念点やデメリット
業務平準化に取り組む上で、以下のような点を課題に感じているご担当者様も多いのではないでしょうか。ここで取りあげる懸念点やデメリットを解消して、業務平準化の施策を成功へ導くために、以降でご紹介する推進方法やソリューションをご検討ください。

導入時に負担が増えるおそれがある
業務平準化へ向けて新たな仕組みやプロセスを導入する場合、計画やテスト運用の期間が必要です。一時的に業務量の増加や従業員の混乱が懸念されます。特に、導入初期段階では作業工数やコストがかさみやすくなります。
業務の柔軟性を低下させる
業務平準化によって作業の負荷やスケジュールが固定されると、急な業務や緊急対応がしにくくなります。その結果、突発的な業務への対応力が落ちたり、市場の変動に柔軟に対応できなったりするおそれがあります。
従業員のモチベーションを低下させる
一部の従業員は、業務平準化にともなう新たな業務配分が負担となることがあります。また、柔軟性のないスケジュールやタスクに不満をおぼえる従業員がいるかもしれません。従業員のモチベーションへの影響に注意が必要です。
業務内容によっては適用が難しい
特定の業種や業務では業務平準化の実現が非現実的であるケースも考えられます。また、業務平準化の適用範囲が限定されることも少なくありません。個々の業務特性を無視した施策は、むしろ効率低下を引き起こすおそれがあります。
業務を平準化するための方法
業務平準化の施策を成功へ導くためには、以下の方法で取り組むと効果的です。また、必要に応じて専用のソリューションを活用する方法もおすすめします。

業務プロセスを可視化する
初めに現状の業務プロセスを可視化して把握し、全体の流れや負荷が集中しているポイントを特定します。その際は、フローチャートや業務分析ツールなどを活用して、視覚的にわかりやすく整理することが重要です。ボトルネックを発見したら、解決へ向けて具体策を検討し、自社の課題に適した手法を選択します。
適切なリソース配分を行う
社内の人員や設備を適切に配置し、作業量に応じてリソースの割り当てを行います。各メンバーのスキルや得意分野を考慮したうえで、チーム全体でタスクをバランスよく振り分けることがポイントです。万が一、不足しているリソースがある場合は、リソースの補充を検討するか、アウトソーシングによる外部リソースの活用を行います。
マニュアルを作成し有効活用する
作業手順を統一して属人化を防止するために、業務マニュアルを作成します。マニュアル作成では文章に加えて図や動画などを活用して、誰もが簡単に理解しやすい形式に資料をまとめる必要があります。また、作成したマニュアルは定期的なチェックを実施して、会社の最新の業務フローに適合させることが大切です。
【法人ビジネス向けモバイル端末+クラウドストレージ Box】
作業マニュアルの管理と閲覧に適した、「法人ビジネス向けモバイル端末」と「クラウドストレージ Box」によるソリューションです。作業マニュアルをクラウドストレージに保存し、業務用タブレットからアクセスする仕組みを構築することで、いつでもどこでもマニュアルを閲覧できるようになります。紙ベースで運用している現状の作業マニュアルを電子化すると、従来よりも検索性や保存性が高まり、社内に蓄積されたナレッジの有効活用を促せます。
法人ビジネス向けモバイル端末の詳しい情報はこちら
クラウドストレージ「Box」の詳しい情報はこちら
法人ビジネス向けモバイル端末の詳しい情報はこちら
クラウドストレージ「Box」の詳しい情報はこちら
作業スケジュールを調整する
業務量のピークを平準化するために、従業員ごとの作業スケジュールを細かく調整します。繁閑の差が大きくなりやすい業務では、必要に応じてシフト制やフレックスタイム制などの柔軟な働き方を導入するのも一つの手です。また、業務スケジュールは短期・中期・長期の視点で管理して、適宜調整できる仕組みを作るのが望ましいといえます。
自動化ツールやシステムを活用する
業務平準化の施策の一環として、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)や管理ツールを導入して効率化する方法です。定型業務や単純作業を自動化することで、より重要性の高い業務へリソースを集中できるようになります。ツール導入後も定期的な効果測定へ取り組み、改善点を洗い出すと効果的です。
【文書仕分けを自動化!KYOCERA Capture Manager】
文書の仕分け作業を自動化するソリューションです。多様な電子文書の仕分けやデータ入力で発生する手作業を削減し、ワークフローの自動化を実現します。例えば、紙で運用している作業指示書や工程表をスキャンして電子化する場合は、手作業でファイルの仕分けやリネームを行う工数が発生します。そんなとき、「KYOCERA Capture Manager」ならスキャンするだけでファイル名を自動設定し、フォルダーに自動保存されるため、大幅な工数削減が期待できます。
KYOCERA Capture Managerの詳しい情報はこちら
KYOCERA Capture Managerの詳しい情報はこちら
定期的な業務改善の取り組みを行う
業務平準化の施策では、PDCAサイクルを回して継続的な見直しと改善に取り組むことが重要となります。その際は、従業員の意見をヒアリングして、現場の課題を今後の施策へ適切に反映させることがポイントです。また、業務改善の結果を周知し、成功事例を組織全体で共有すると従業員のモチベーション向上につなげられます。
業務平準化を進めるうえでの注意点
業務平準化を推進する際は、以下の注意点を押さえて取り組むことが大切です。プロジェクトに全社的な協力を得るとともに、長期的な視点をもって実施するために、ぜひ参考にしてみてください。

従業員の負担や反発に配慮する
業務平準化の施策は、社員の協力を得て全社的に取り組むことが重要です。導入によって一時的に従業員に負担が生じる可能性があるため、事前に十分な説明やサポートを行う必要があります。また、環境の変化にともなう従業員の反発を避けるには、具体的なメリットを伝える対策が有効です。従業員の意見や提案を積極的に取り入れ、現場の声を尊重する姿勢を示すこともポイントとなります。
現場の実情を無視した計画を立てない
業務平準化を推進する際は、現場の実情を考慮した施策を検討します。そのためには、現場ごとの業務内容や課題を正確に把握し、課題に即した計画を策定することが重要です。事前の調査やヒアリングを丁寧に実施し、テスト運用で問題がないか確認を行います。一律の進め方や手法を押し付けるのではなく、現場と連携して柔軟にプロジェクトを遂行するのが望ましいといえます。
短期的な効果だけを追求しない
業務平準化は短期的な成果を追求するよりも、長期的な効率化や安定化を目指した施策となります。目先のコスト削減にこだわるあまり、業務品質や従業員のモチベーションを損なわないように注意が必要です。また、定期的な効果測定を実施するには、事前に評価基準を設定するとともに、一定期間ごとに評価と見直しを実施する仕組みを作る必要があります。
業務プロセスの変更に伴うリスクを考慮する
業務平準化へ向けて既存の業務プロセスを変更する場合は、一時的な混乱や業務停止のリスクを最小限に抑えるための対策が求められます。業務プロセスの変更で発生するトラブルを予測し、あらかじめ代替案やバックアップ体制を準備しておくことが重要です。また、新たな業務プロセスが想定した通りに機能しない場合に備えて、一部の業務へ段階的に導入する方法をおすすめします。
適切なコミュニケーションを確保する
業務平準化の推進には、経営陣から現場の社員まで全員が共通の理解を持つために、社内で情報を共有する必要があります。適切なコミュニケーションを確保して、業務平準化の目的や効果をわかりやすく伝えることによって、従業員の理解を促せるようになります。進捗状況や課題について適宜話し合い、関係者全員の意見を反映させることが重要です。
業務平準化による職場の改善を目指しましょう
ここまで業務平準化に関する基礎知識をお伝えしました。業務平準化を推進すると、「作業負荷の均一化」「生産性向上」「業務品質の安定化」「コスト削減」といった多くのメリットが期待できます。施策を成功へ導くために、自動化ツールやシステムを活用すると効果的です。京セラドキュメントソリューションズジャパンでは、業務改善を目指す企業様のニーズに対応した各種ソリューションをご提供しています。システム化で現場の課題を解決するために、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お役立ち資料
アナログ業務の効率化、作業ミス削減を実現する方法は?
本資料では、現場におけるアナログ業務の弊害、解決方法、解決事例をご紹介します。現場業務の効率化やミス削減を推進している方におすすめです。
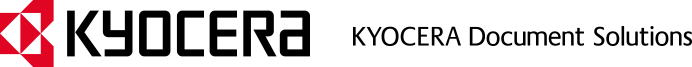
京セラドキュメントソリューションズジャパンが提供するお役立ちコラムでは、業務上の課題解決のヒントや、現在のビジネストレンドなど、知っておきたい情報を業種やテーマごとに発信しております。また、ペーパーレス化やセキュリティー強化などを詳しく解説したお役立ち資料を無料で公開しておりますので、ぜひご覧ください。